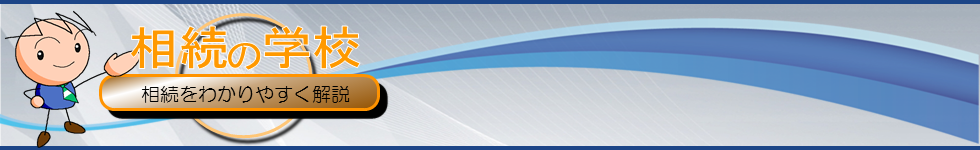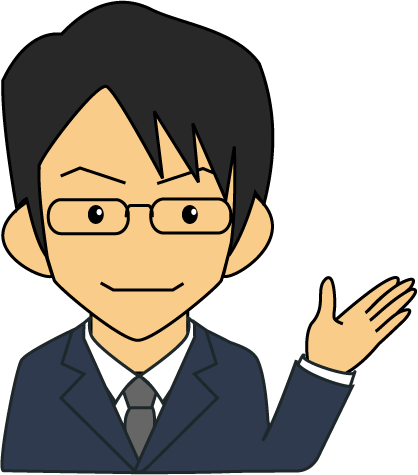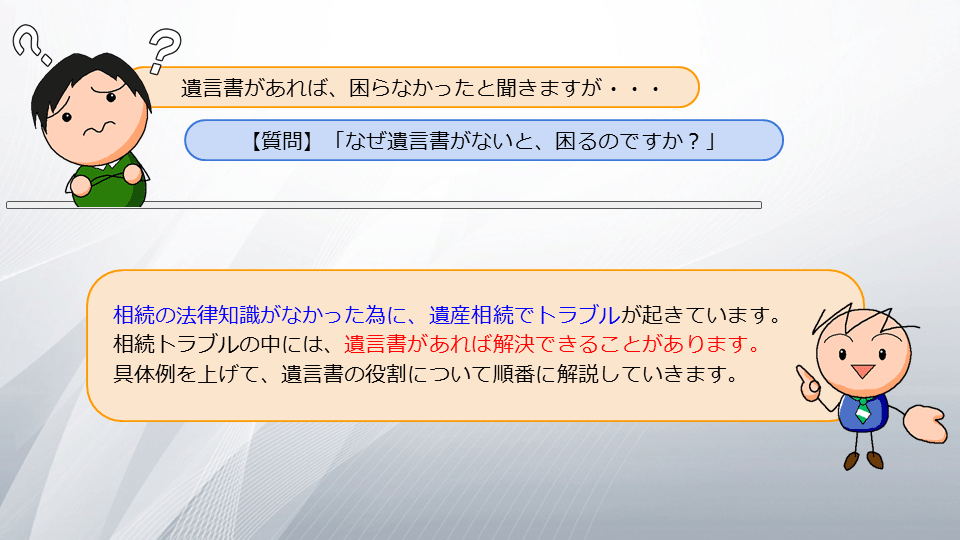
遺言書があれば、困らなかったと聞きますが・・・
【質問】「なぜ遺言書がないと、困るのですか?」
相続の法律知識がなかった為に、遺産相続でトラブルが起きています。
相続トラブルの中には、遺言書があれば解決できることがあります。
具体例を上げて、遺言書の役割について順番に解説していきます。
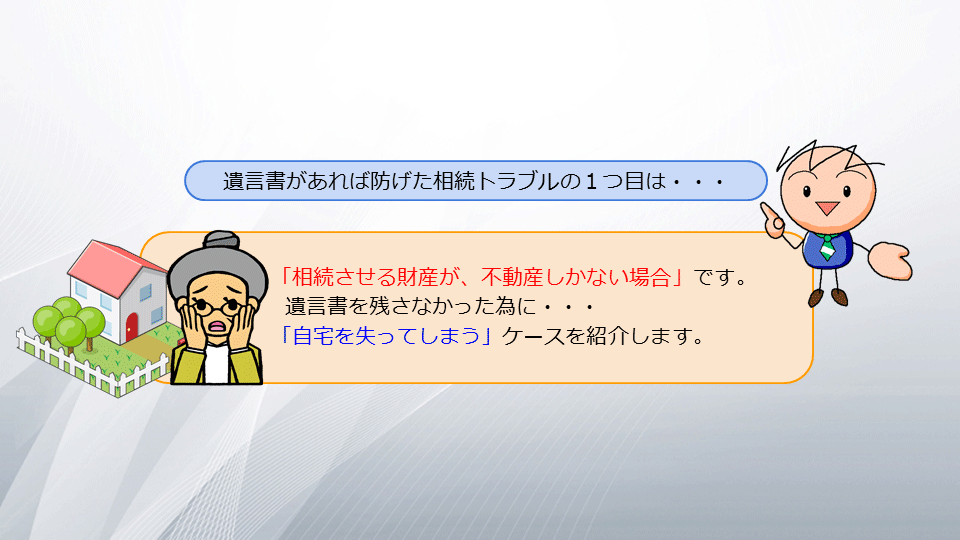
遺言書があれば防げた相続トラブルの1つ目は・・・
「相続させる財産が、不動産しかない場合」です。
遺言書を残さなかった為に「自宅を失ってしまう」ケースを紹介します。
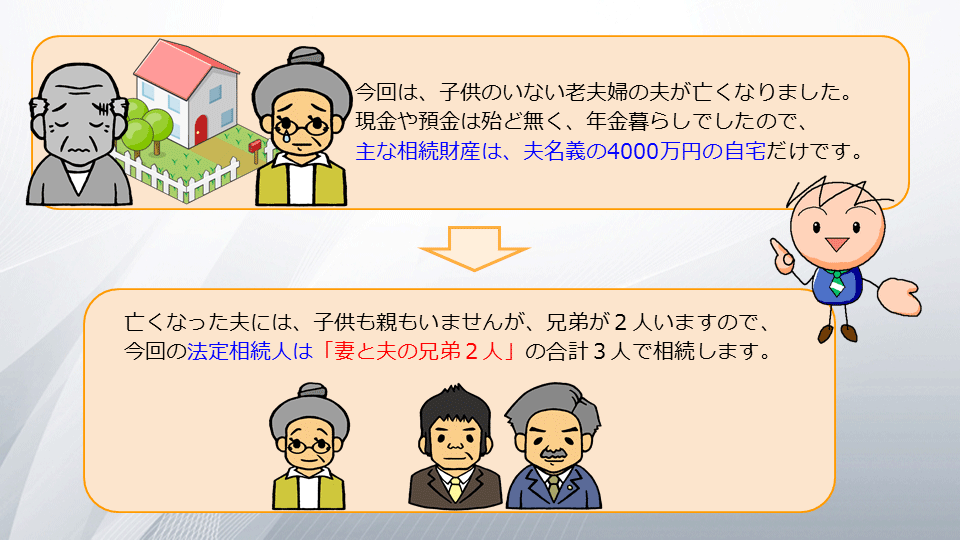
今回は、子供のいない老夫婦の夫が亡くなりました。
現金や預金は殆ど無く、年金暮らしでしたので、
主な相続財産は、夫名義の4000万円の自宅だけです。
↓
亡くなった夫には、子供も親もいませんが、兄弟が2人いますので、
今回の法定相続人は「妻と夫の兄弟2人」の合計3人で相続します。
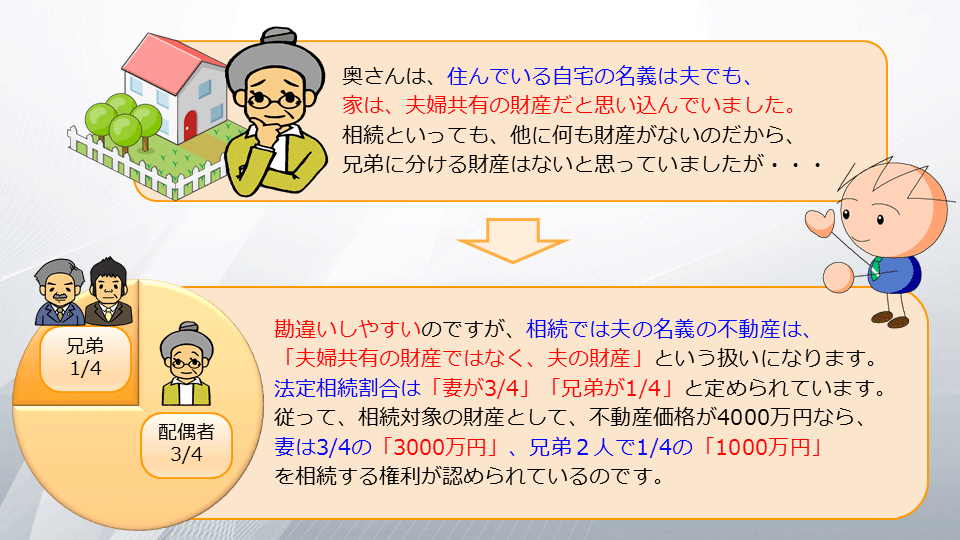
奥さんは、住んでいる自宅の名義は夫でも、
家は、夫婦共有の財産だと思い込んでいました。
相続といっても、他に何も財産がないのだから、
兄弟に分ける財産はないと思っていましたが・・・
↓
勘違いしやすいのですが、相続では夫の名義の不動産は、
「夫婦共有の財産ではなく、夫の財産」という扱いになります。
法定相続割合は「妻が3/4」「兄弟が1/4」と定められています。
従って、相続対象の財産として、不動産価格が4000万円なら、
妻は3/4の「3000万円」、兄弟2人で1/4の「1000万円」
を相続する権利が認められているのです。
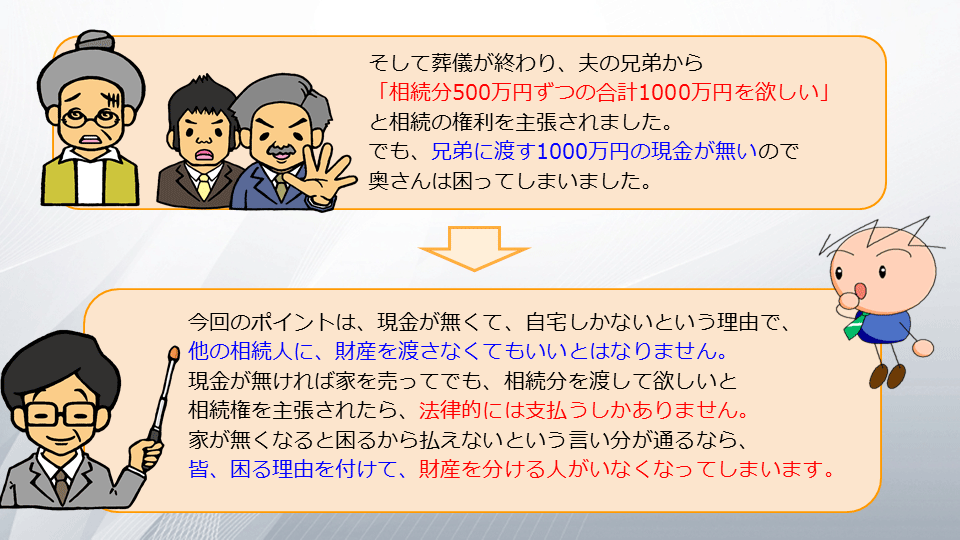
そして葬儀が終わり、夫の兄弟から
「相続分500万円ずつの合計1000万円を欲しい」と相続の権利を主張されました。
でも、兄弟に渡す1000万円の現金が無いので、奥さんは困ってしまいました。
↓
今回のポイントは、現金が無くて、自宅しかないという理由で、
他の相続人に、財産を渡さなくてもいいとはなりません。
現金が無ければ家を売ってでも、相続分を渡して欲しいと
相続権を主張されたら、法律的には支払うしかありません。
家が無くなると困るから払えないという言い分が通るなら、
皆、困る理由を付けて、財産を分ける人がいなくなってしまいます。
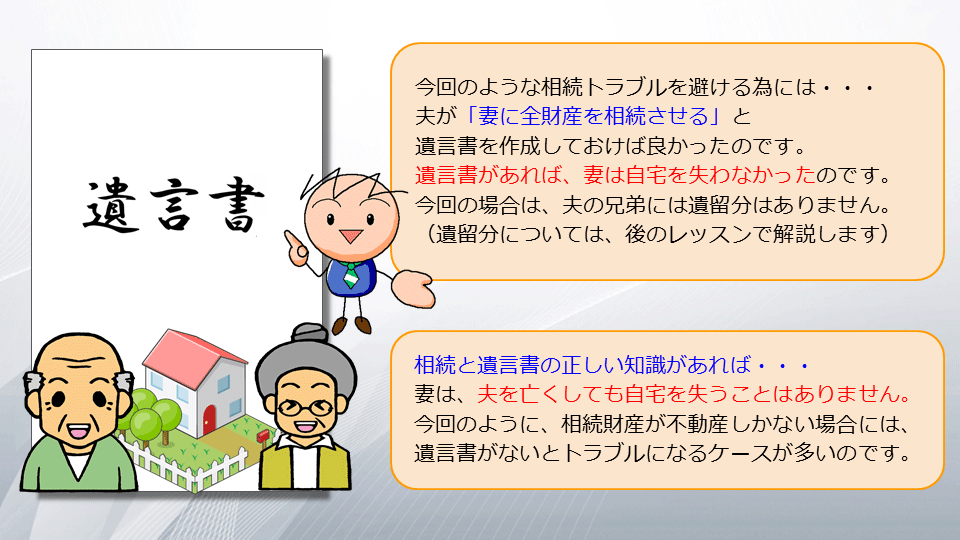
今回のような相続トラブルを避ける為には・・・
夫が「妻に全財産を相続させる」と遺言書を作成しておけば良かったのです。
遺言書があれば、妻は自宅を失わなかったのです。
今回の場合は、夫の兄弟には遺留分はありません。
(遺留分については、後のレッスンで解説します)
相続と遺言書の正しい知識があれば、妻は夫を亡くしても自宅を失うことはありません。
今回のように、相続財産が不動産しかない場合には、
遺言書がないとトラブルになるケースが多いのです。
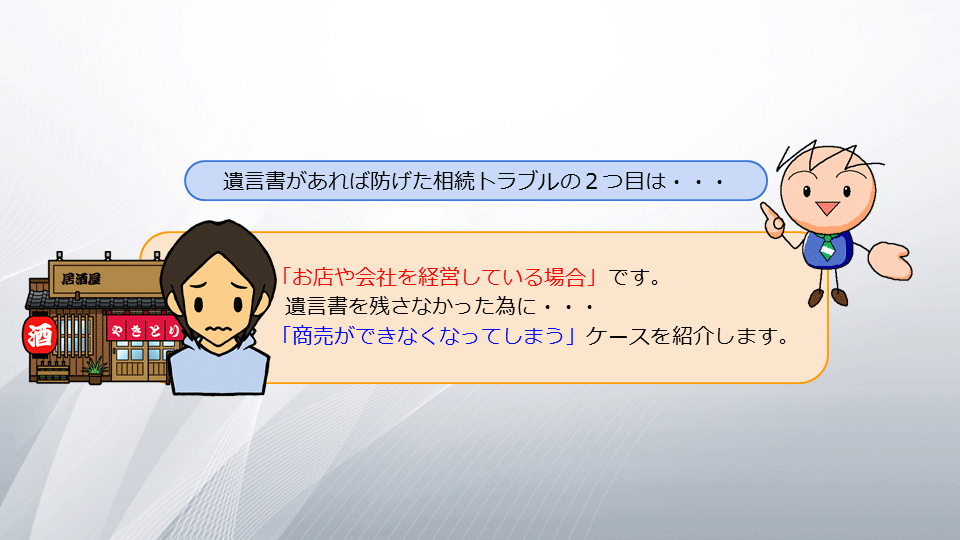
遺言書があれば防げた相続トラブルの2つ目は・・・
「お店や会社を経営している場合」です。
遺言書を残さなかった為に・・・
「商売ができなくなってしまう」ケースを紹介します。
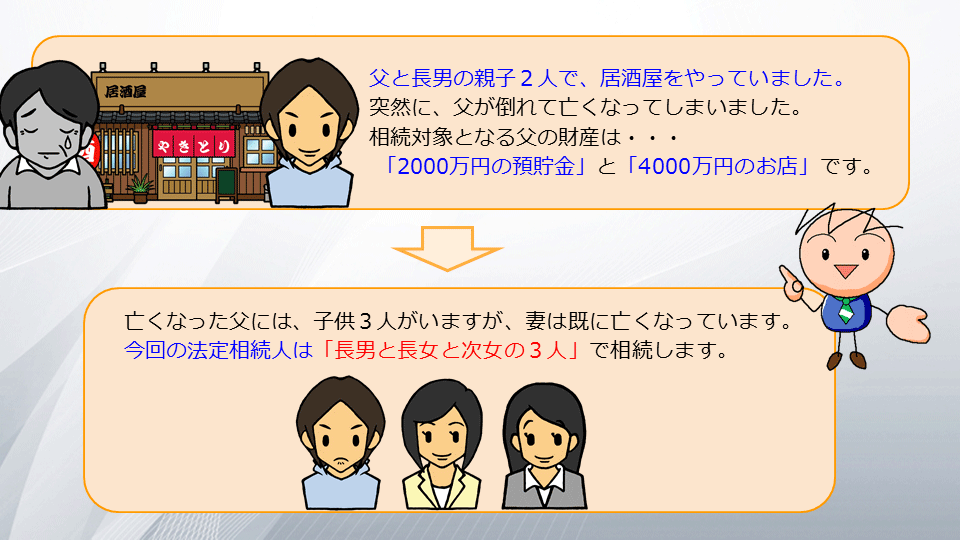
父と長男の親子2人で、居酒屋をやっていました。
突然に、父が倒れて亡くなってしまいました。
相続対象となる父の財産は・・・
「2000万円の預貯金」と「4000万円のお店」です。
↓
亡くなった父には、子供3人がいますが、妻は既に亡くなっています。
今回の法定相続人は「長男と長女と次女の3人」で相続します。
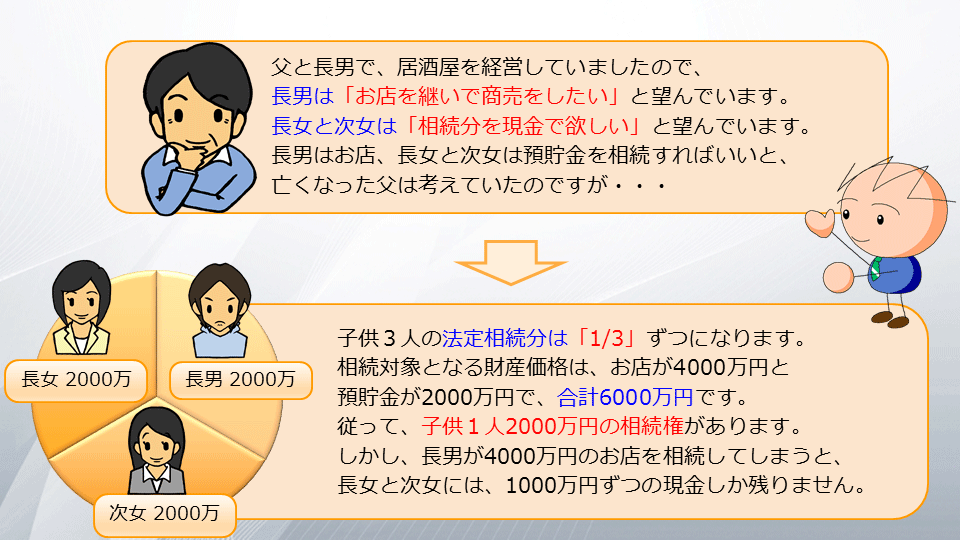
父と長男で、居酒屋を経営していましたので、
長男は「お店を継いで商売をしたい」と望んでいます。
長女と次女は「相続分を現金で欲しい」と望んでいます。
長男はお店、長女と次女は預貯金を相続すればいいと、
亡くなった父は考えていたのですが・・・
↓
子供3人の法定相続分は「1/3」ずつになります。
相続対象となる財産価格は、お店が4000万円と
預貯金が2000万円で、合計6000万円です。
従って、子供1人2000万円の相続権があります。
しかし、長男が4000万円のお店を相続してしまうと、
長女と次女には、1000万円ずつの現金しか残りません。
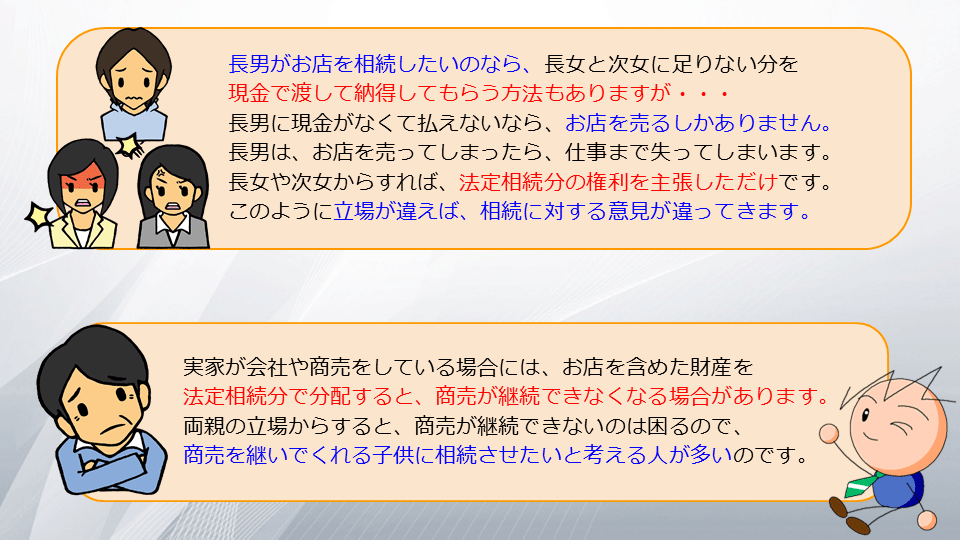
長男がお店を相続したいのなら、長女と次女に足りない分を
現金で渡して納得してもらう方法もありますが・・・
長男に現金がなくて払えないなら、お店を売るしかありません。
長男は、お店を売ってしまったら、仕事まで失ってしまいます。
長女や次女からすれば、法定相続分の権利を主張しただけです。
このように立場が違えば、相続に対する意見が違ってきます。
実家が会社や商売をしている場合には、お店を含めた財産を
法定相続分で分配すると、商売が継続できなくなる場合があります。
両親の立場からすると、商売が継続できないのは困るので、
商売を継いでくれる子供に相続させたいと考える人が多いのです。
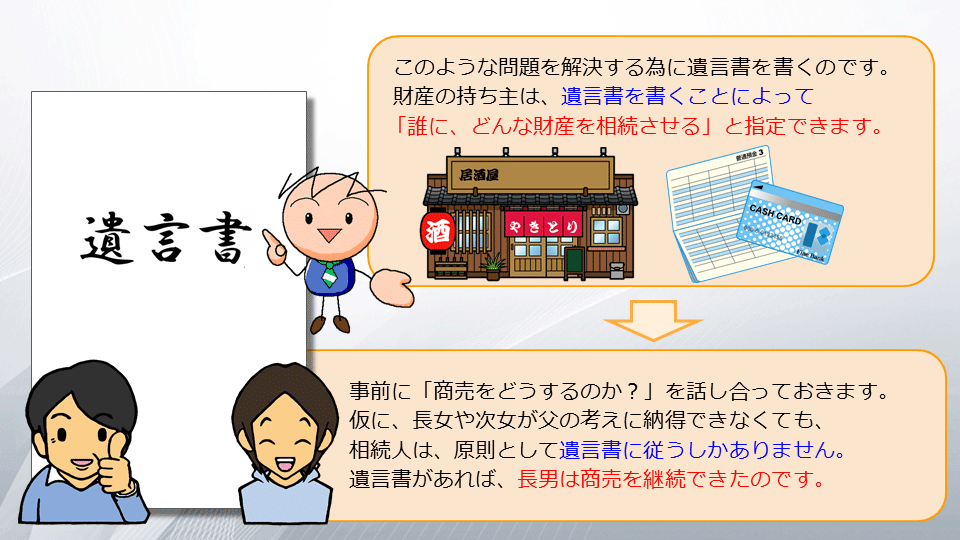
このような問題を解決する為に遺言書を書くのです。
財産の持ち主は、遺言書を書くことによって
「誰に、どんな財産を相続させる」と指定できます
↓
事前に「商売をどうするのか?」を話し合っておきます。
仮に、長女や次女が父の考えに納得できなくても、
相続人は、原則として遺言書に従うしかありません。
遺言書があれば、長男は商売を継続できたのです。
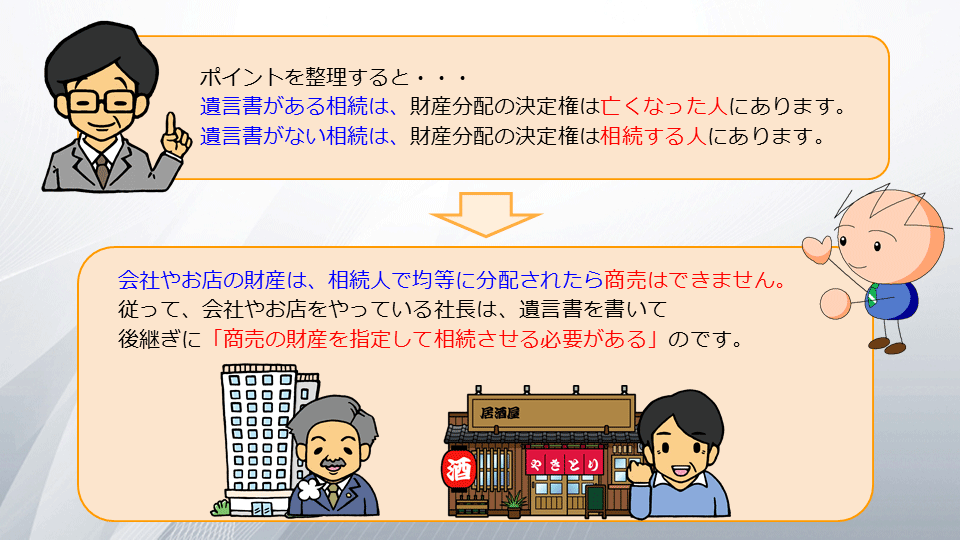
ポイントを整理すると・・・
遺言書がある相続は、財産分配の決定権は亡くなった人にあります。
遺言書がない相続は、財産分配の決定権は相続する人にあります。
↓
会社やお店の財産は、相続人で均等に分配されたら商売はできません。
従って、会社やお店をやっている社長は、遺言書を書いて
後継ぎに「商売の財産を指定して相続させる必要がある」のです。
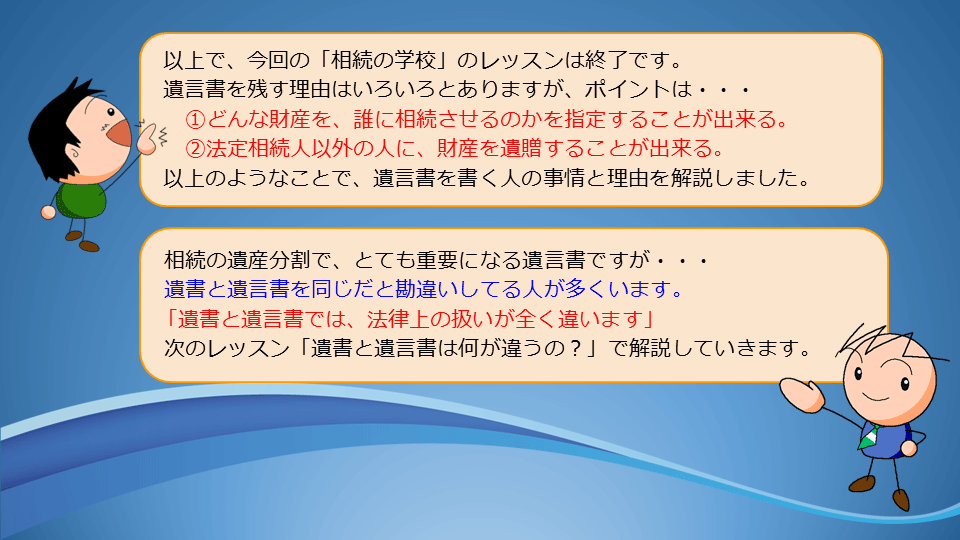
以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。
遺言書を残す理由はいろいろとありますが、ポイントは・・・
①どんな財産を、誰に相続させるのかを指定することが出来る。
②法定相続人以外の人に、財産を遺贈することが出来る。
以上のようなことで、遺言書を書く人の事情と理由を解説しました。
相続の遺産分割で、とても重要になる遺言書ですが・・・
遺書と遺言書を同じだと勘違いしてる人が多くいます。
「遺書と遺言書では、法律上の扱いが全く違います」
次のレッスン「遺書と遺言書は何が違うの?」で解説していきます。
| 目次 | 次へ |