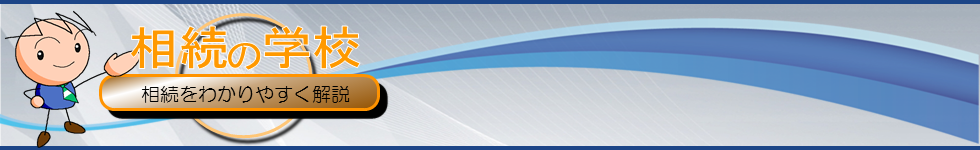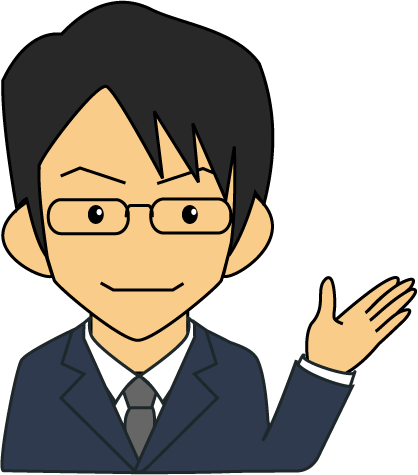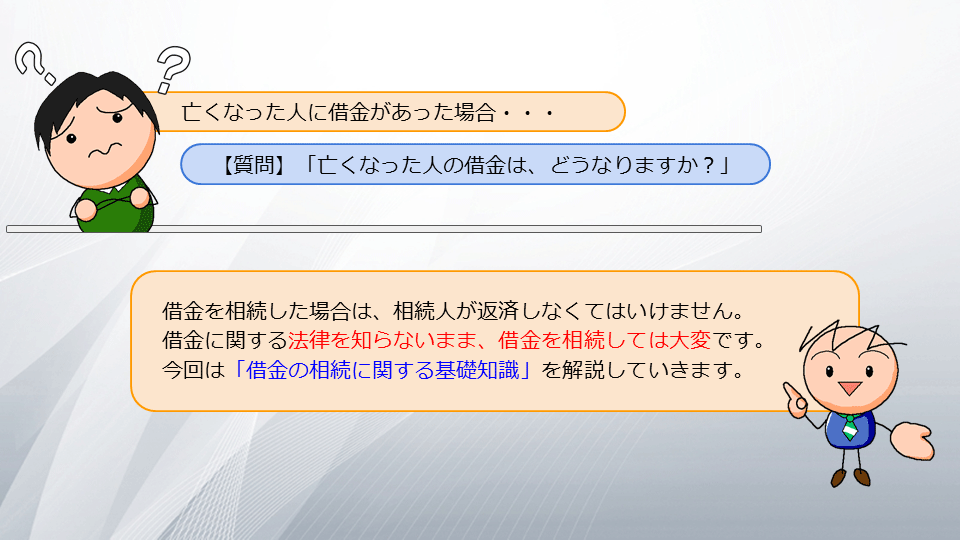
亡くなった人に借金があった場合・・・
【質問】「亡くなった人の借金は、どうなりますか?」
借金を相続した場合は、相続人が返済しなくてはいけません。
借金に関する法律を知らないまま、借金を相続しては大変です。
今回は「借金の相続に関する基礎知識」を解説していきます。
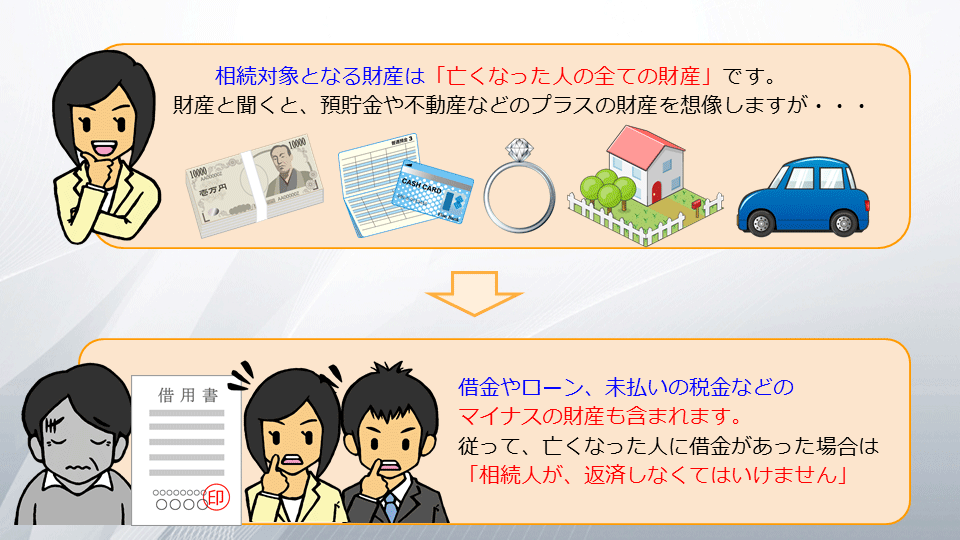
相続対象となる財産は「亡くなった人の全ての財産」です。
財産と聞くと、預貯金や不動産などのプラスの財産を想像しますが・・・
↓
借金やローン、未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
従って、亡くなった人に借金があった場合は「相続人が、返済しなくてはいけません」
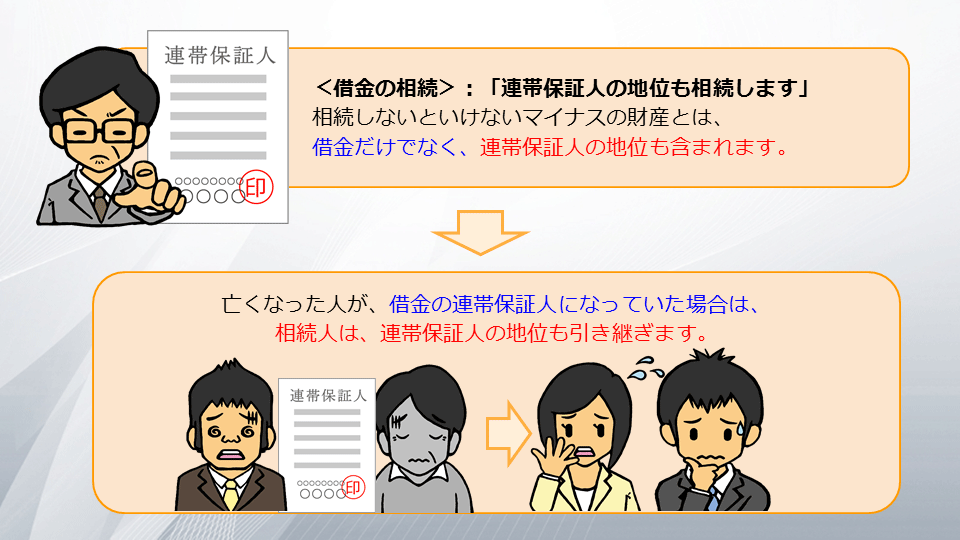
<借金の相続>:「連帯保証人の地位も相続します」
相続しないといけないマイナスの財産とは、借金だけでなく、連帯保証人の地位も含まれます。
↓
亡くなった人が、借金の連帯保証人になっていた場合は、
相続人は、連帯保証人の地位も引き継ぎます。
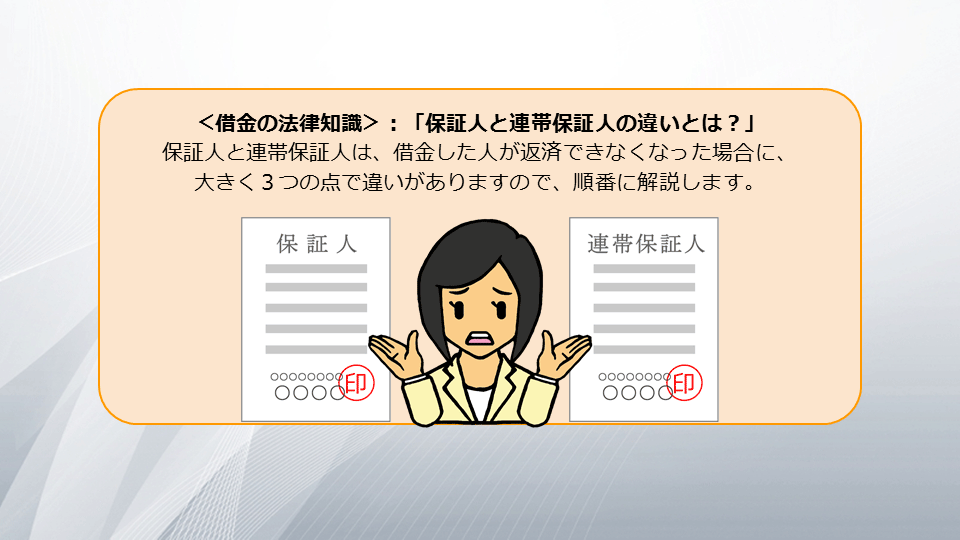
<借金の法律知識>:「保証人と連帯保証人の違いとは?」
保証人と連帯保証人は、借金した人が返済できなくなった場合に、
大きく3つの点で違いがありますので、順番に解説します。
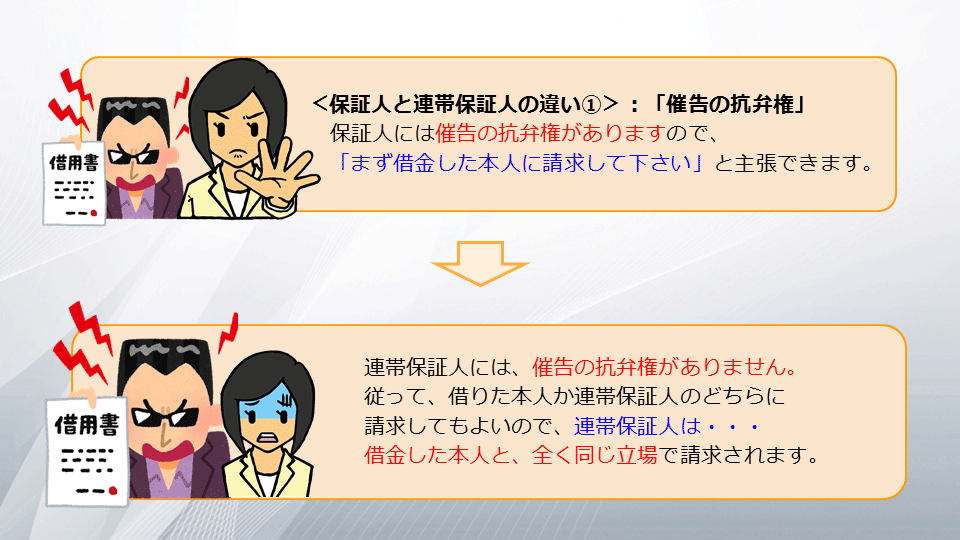
<保証人と連帯保証人の違い①>:「催告の抗弁権」
保証人には催告の抗弁権がありますので、「まず借金した本人に請求して下さい」と主張できます。
↓
連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。
従って、借りた本人か連帯保証人のどちらに請求してもよいので、
連帯保証人は・・・借金した本人と、全く同じ立場で請求されます。
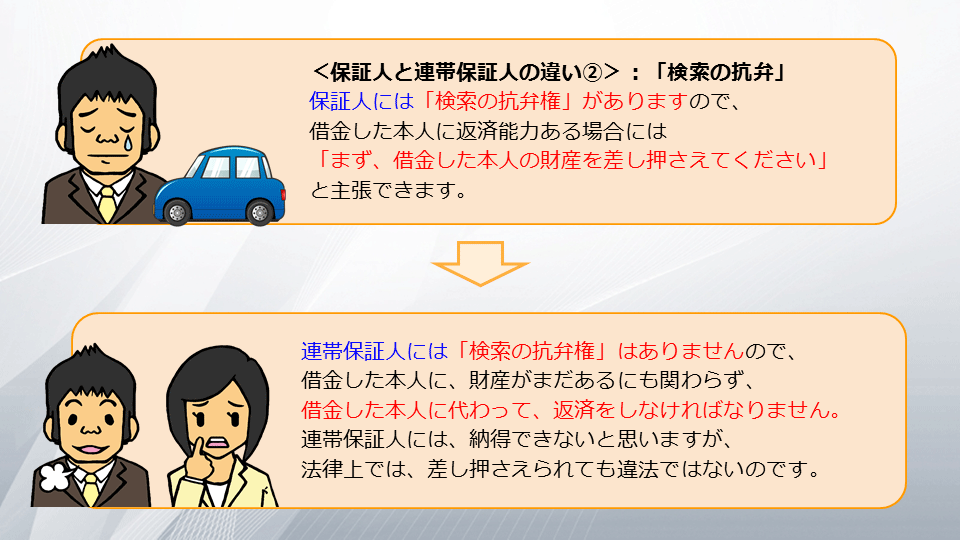
<保証人と連帯保証人の違い②>:「検索の抗弁」
保証人には「検索の抗弁権」がありますので、借金した本人に返済能力ある場合には
「まず、借金した本人の財産を差し押さえてください」と主張できます。
↓
連帯保証人には「検索の抗弁権」はありませんので、借金した本人に、
財産がまだあるにも関わらず、借金した本人に代わって、返済をしなければなりません。
連帯保証人には、納得できないと思いますが、法律上では、
差し押さえられても違法ではないのです。
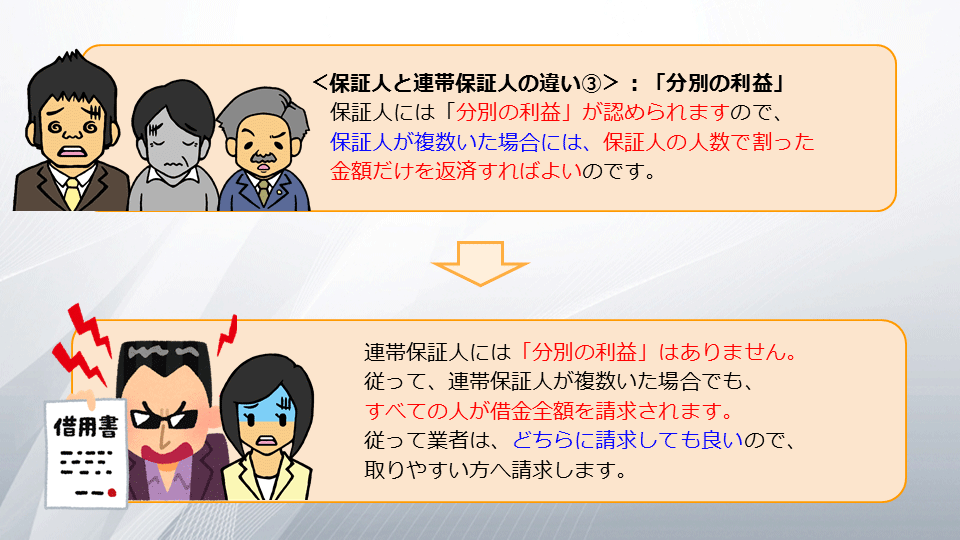
<保証人と連帯保証人の違い③>:「分別の利益」
保証人には「分別の利益」が認められますので、保証人が複数いた場合には、
保証人の人数で割った金額だけを返済すればよいのです。
↓
連帯保証人には「分別の利益」はありません。
従って、連帯保証人が複数いた場合でも、すべての人が借金全額を請求されます。
従って業者は、どちらに請求しても良いので、取りやすい方へ請求します。
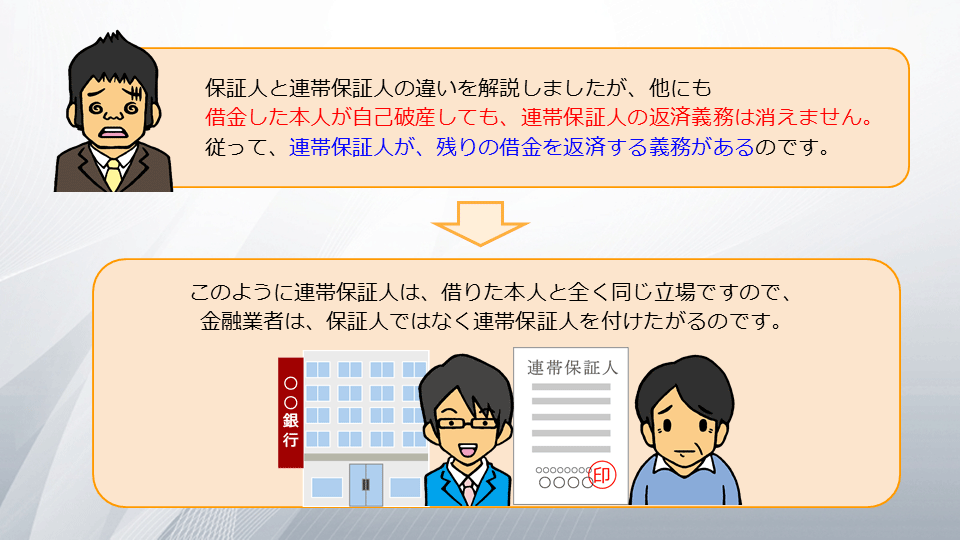
保証人と連帯保証人の違いを解説しましたが、他にも
借金した本人が自己破産しても、連帯保証人の返済義務は消えません。
従って、連帯保証人が、残りの借金を返済する義務があるのです。
↓
このように連帯保証人は、借りた本人と全く同じ立場ですので、
金融業者は、保証人ではなく連帯保証人を付けたがるのです。
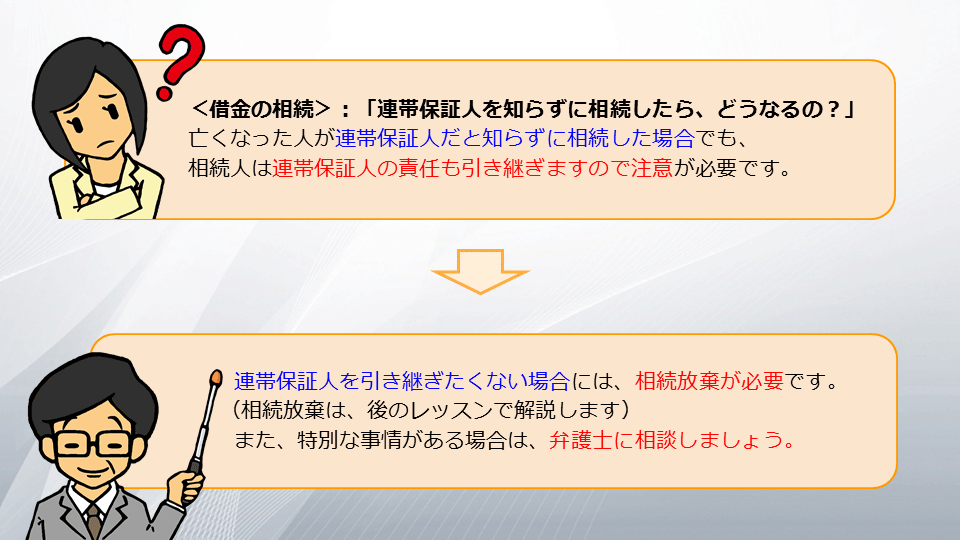
<借金の相続>:「連帯保証人を知らずに相続したら、どうなるの?」
亡くなった人が連帯保証人だと知らずに相続した場合でも、
相続人は連帯保証人の責任も引き継ぎますので注意が必要です。
連帯保証人を引き継ぎたくない場合には、相続放棄が必要です。
↓
(相続放棄は、後のレッスンで解説します)
また、特別な事情がある場合は、弁護士に相談しましょう。
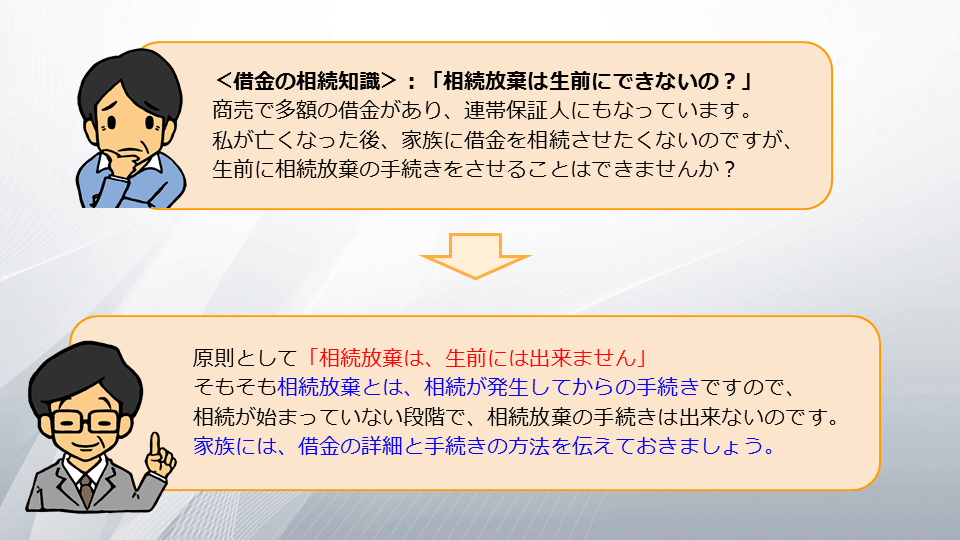
<借金の相続知識>:「相続放棄は生前にできないの?」
商売で多額の借金があり、連帯保証人にもなっています。
私が亡くなった後、家族に借金を相続させたくないのですが、
生前に相続放棄の手続きをさせることはできませんか?
↓
原則として「相続放棄は、生前には出来ません」
そもそも相続放棄とは、相続が発生してからの手続きですので、
相続が始まっていない段階で、相続放棄の手続きは出来ないのです。
家族には、借金の詳細と手続きの方法を伝えておきましょう。
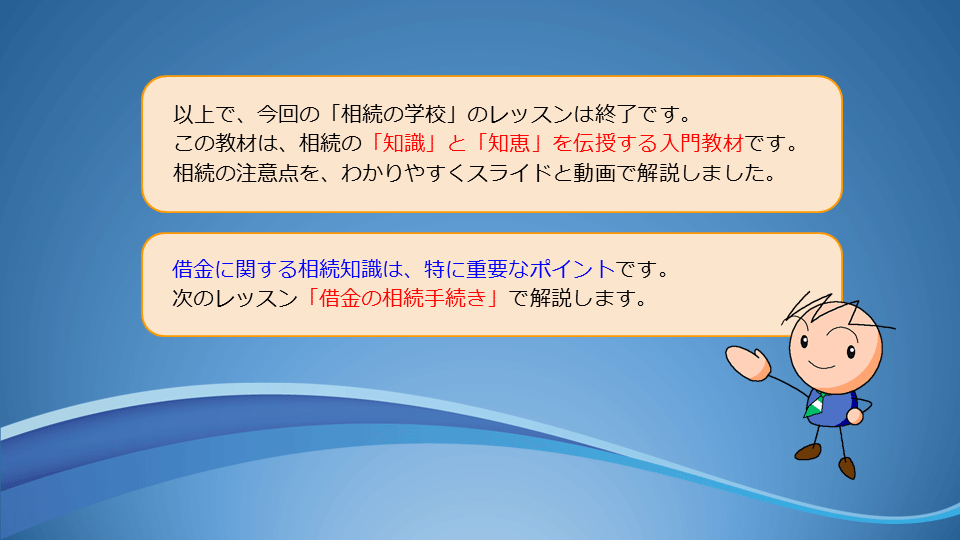
以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。
この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。
相続の注意点を、わかりやすくスライドと動画で解説しました。
借金に関する相続知識は、特に重要なポイントです。
次のレッスン「借金の相続手続き」で解説します。
| 目次 | 次へ |